エレキギターの総合情報サイト
エレキギターの総合情報サイト
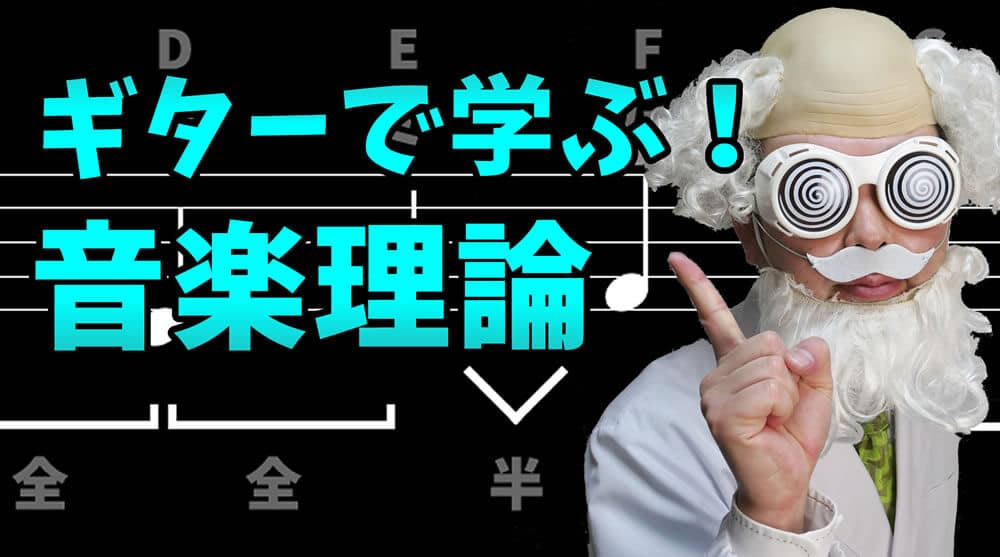
「ドレミファソラシド」の音階・音程を理解すれば、アドリブや作曲で“どの音を使えばいいか”が見えてきます。コードの仕組みを知れば、伴奏やフレーズ作りの幅が広がります。ペンタトニック、ドリアン、フリジアンなどのスケールを覚えることで、ブルースの味わい深さからジャズの洗練、メタルの重厚なリフからソロまで、自分のプレイに多彩な表情を加えられるでしょう。
ここでは、基礎的な半音・全音の仕組みから、コード進行やスケール応用まで、ギタリストが実践で役立つ音楽理論を丁寧に解説していきます。暗記ではなく「なぜそうなるのか」を理解することで、理論をそのまま演奏力に直結させることができます。ギターを通じて音楽理論の世界を楽しく深めていきましょう。
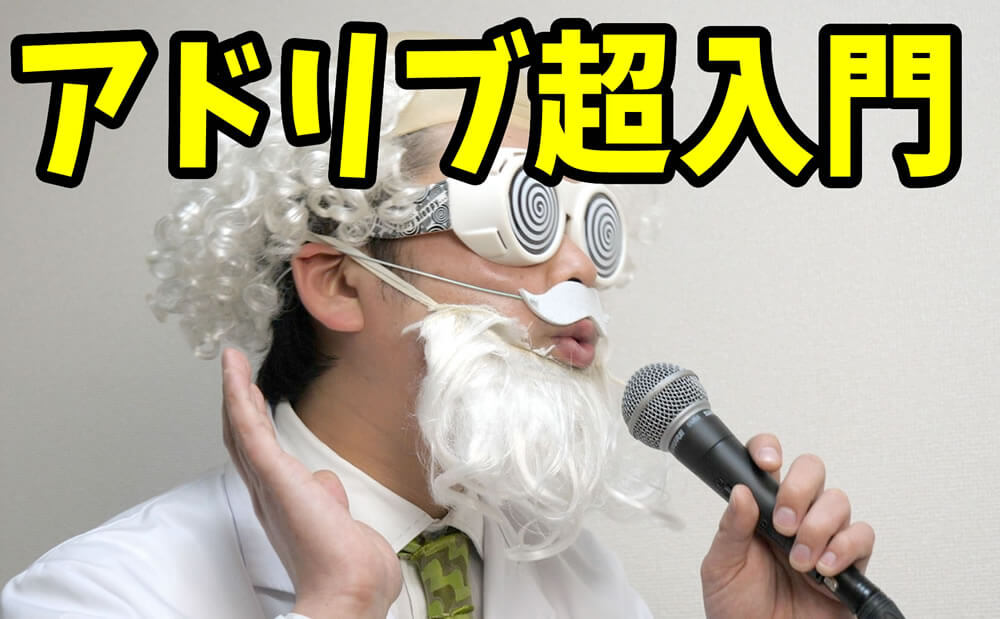
アドリブのギターソロに挑戦したい、セッションに興味がある、しかし何から練習すればよいのかわからない、という人は大勢います。アドリブと聞いて、多くの人は「スケールやコードトーンなどの理論的な勉強が必要なんだろうな」と感じると思います。
事実それは必要になってきますが、最も大切なことは「何が弾きたいか、どんな音を、どんなメロディを弾きたいか」ということです。次のページは「これからアドリブ/アレンジやってみたい!」と思っている人に向けた記事です。
詳しくみる:
アドリブ/アレンジに挑戦してみよう!
音楽理論の基礎は、楽譜を読む人だけでなく、ギターやピアノを演奏する人にとっても重要な知識です。「半音と全音」の仕組みや「音程と度数」の考え方、そして曲の「キー」の理解は、コード進行やスケールを使いこなすための土台になります。まずは音楽理論の入り口をのぞいてみましょう。
コード(和音)はギターやピアノを弾く上で欠かせない要素です。基本はルート音(根音)に他の音を積み重ねて成り立ちますが、その組み合わせ方によって明るい響きや切ない響き、緊張感のある響きなど、多彩な表情を生み出せます。
この項目では、メジャーやマイナーといった三和音の成り立ちから始め、メジャーセブンスやマイナーセブンスといった4声和音の成り立ちまで、順を追って学んでいきます。コードの仕組みを理解すれば、楽曲の分析や作曲はもちろん、演奏中の「なぜこの響きになるのか」が見えてきて、音楽の楽しみ方がぐっと広がります。
楽譜に音名や度数を書き込むと、音楽表現の幅が広がるって本当?
この問いに、博士は「本当です。」と断言します。
音楽表現のステップアップのために、TAB譜だけでなく5線譜も読み、音名や度数などいろいろな情報を書き込んでみましょう。これを実践することで音階や音程、キーやコードなどの知識がギターの練習に結び付き、自分の弾いている音が何か、コードの中でどのように響いているのか、どのように上下しているのかといった音楽の仕組みが分かるようになります。
すると音のイメージがより鮮明になり、指板上に音が見えるようになり、まだ知らない表現を考案できるようにもなり、あなたの音楽表現は今以上に豊かになっていくでしょう。こうした「音楽力」が身についてくると、たくさんの新しい道や希望が見えるようになります。作曲や編曲など、自分でもまだ気付いていない可能性を引き出すきっかけになるかもしれません。頑張ってくださいね!
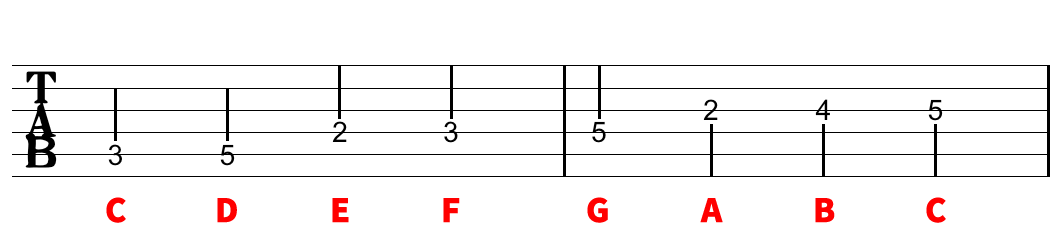
スケールはただ闇雲にポジションを覚えるのではなく、「仕組み」と「覚え方のコツ」を押さえることで感覚的に理解できます。どんなスケールも根本にある考え方は同じなので、一度コツをつかんで応用できるようになれば、ロックでもジャズでも活用できるようになります。
まずは一番身近でわかりやすいメジャースケールを例に、その覚え方のポイントを確認してみましょう。音楽的な感覚を育てるためのヒントは以下のリンクにまとめていますので、ぜひチェックしてみてください。
基礎的なコードの仕組みを理解したら、次はそれをどのように音楽の中で使うかを学んでいきましょう。この項目では、メジャー・ダイアトニックやマイナー・キーのコード進行、Ⅱ–Ⅴ–Ⅰといった定番の流れ、さらにはセカンダリー・ドミナントやサブドミナント・マイナーといった発展的な和音の考え方まで幅広く扱います。
ポップスやジャズ、ブルースなど実際のジャンルでよく登場する進行を通じて、コードがどんな役割を持ち、どう響きを変化させているのかが見えてくるでしょう。単なる暗記ではなく「なぜそうなるのか」を理解することで、作曲やアドリブ演奏に直結する音楽的な発想力を磨くことができます。
ここまででコード理論の応用を一通り学びましたが、知識は実際の音楽に触れてこそ定着します。ぜひ好きな曲を聴きながら、「次の進行はトニックかな?」「Ⅱ–Ⅴ–Ⅰが出てきた!」と自分なりに分析してみましょう。頭で理解した理論が耳と指に結びつくと、ぐっと音楽が面白くなります。






スケールは単なる「音の並び」ではなく、フレーズやコード進行に対して“どんな音を選ぶか”の地図のような役割を果たします。ギターを弾くとき、感覚だけに頼って音を並べると“なんとなく”で終わりがちですが、スケールを理解すれば「この場面ではこの音がハマる」という根拠を持って演奏できます。
スケールを学んでいくとよく登場するのが「モード」という言葉です。モードとは、簡単にいうと「メジャースケールをどの音からスタートするかによって生まれる音階の種類」のことです。
例えばCメジャースケールは「C D E F G A B」という七つの音でできていますが、この同じ七つの音を、Cから始めればCアイオニアン、Dから始めればDドリアン、Eから始めればEフリジアン……といった具合に、スタート地点を変えるだけで七種類のモードが生まれます。これらのモードは古代ギリシャの教会で使われていたことから「教会旋法」と呼ばれます。
モードを理解すると、コードごとに適したスケールを選択できるようになります。たとえば「C△7」に対してはアイオニアンだけでなくリディアンを選ぶことで浮遊感を演出できるなど、コードとスケールの関係をより柔軟に使い分けられます。
ロック系の音楽はワンコードのアドリブ(ギターソロ)が多く、しかもキーボードがいない場合、コード感がはっきりと示されない傾向があります。こういった場面ではモードを用いるととても都合が良いのです。
例えば3ピースのバンドでギタリストがソロを弾いているときには、コード楽器がなくなりドラムのリズムとベースの低音が主なバッキングとなります。すると極端にいえば、ベーシストの弾くルート音以外の音は、ギタリストがどんなスケールを弾くかで決まってしまうことになり、結果的にギタリストは大変に大きな自由を手に入れることになります。
マイナーの曲でソロを弾く場合、ありきたりな感じならマイナーペンタトニックスケールやナチュラルマイナースケールを使えば良いし、少しモダンにしたければドリアンスケール、フラメンコのような感じが欲しければフリジアンスケール、クラシカルにしたければハーもニックマイナースケール、というように自由にスケールを使い分けることが可能となるのです。
お久しぶり生放送:ぐだぐだゾ?〜理論の話〜好きなギタリストの話〜基礎練習の話
20:10〜 ギター博士が考える音楽理論について

ギター博士「音楽理論とは何ぢゃろうか。「ミュージシャンの共通言語」「音楽と自分を結ぶためのもの」「音楽的な常識」など、わしは人それぞれ、いろいろな考えがあって良いと思うんぢゃ。
わしが思う音楽理論は、「音楽を学ぶための道具」ぢゃ。覚えた途端に全てが手に入るような理想的な何かではなくて、あくまでも道具ぢゃ。
音楽理論という道具を使うことで、自分の好きな曲ややりたいことを分析することができる。
メカニズムを知ったり、分解したり、改造したり、自分で構築したりもできるんぢゃ。
自分の好きないくつかのものが、同じ特徴を持っていた、なんてことが分かったりもする。
そういった経験的に得た知識を「ピン留め」して積み重ねた音楽のノウハウが、わしの言う「マイ理論」ぢゃ。
ミュージシャンにとって、コレはひじょうに重要なものだと思っておるんぢゃ。
「音理論なんて知らなくても、作曲はできるしギターも弾ける」
「音楽理論を知らなくても活躍しているアーティストはいる」
まったくもって、その通りぢゃ。
音楽理論は道具であって、音楽を学ぶ前の段階で学ぶものだから、プレイや作曲に直接影響するわけではない。
しかし、美しい音楽やかっこいいフレーズを自分の中にピン留めするためには、必要だと思っておる。
音楽のエッセンスをピン留めしていくことで、自分の世界が広がる。
音楽理論を使えば、それらがどんなものなのかが言葉で整理できるんぢゃ。
音楽理論が自分の役に立つのか?厳しい意見かもしれんが、役立たせるのは自分ぞ。
好きな曲に隠された秘密、どうしても知りたい。しかし誰かが教えてくれるわけではない。そんな時は、自分でやるしかないんぢゃ。音楽理論の習得、ぜひ挑戦してみて欲しい。

音楽理論・音楽論 の 売れ筋ランキングを…
Aアマゾンで探す
※当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品を紹介しています。

guitar-hakase.com

guitar-hakase.com

guitar-hakase.com

guitar-hakase.com

guitar-hakase.com

guitar-hakase.com

guitar-hakase.com

guitar-hakase.com
