エレキギターの総合情報サイト
エレキギターの総合情報サイト

一言で「エレキギター」と言っても、ボディ構造の違いによって
このように大きく3種類に分類されます。フルアコとセミアコを合わせて「ハコモノ」とも言われます。
solid:中まで堅い。身が詰まっている。
hollow:中空の。中に空洞がある。
英語では、「ソリッド」と「ホロウ」が対義語になっています。
それぞれどんな特徴があり、どんなサウンドなのでしょうか。ギター博士が愛用の三本を弾き比べている動画がありますので、チェックしてみましょう。
基本的にどのサウンドもリバーブ、ディレイを薄くかけて奥行きを出しています。
クリーントーン時は TC Electronic のコンプレッサー「HYPERGRAVITY COMPRESSOR」をONに。
軽く歪ませている時はElectro Harmonix Crayonを、ディストーションにはBlackstar LT-Distを使っています。
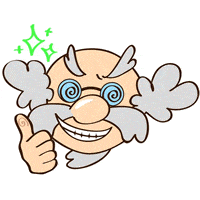
今回は3種類のエレキギターを弾いたわけぢゃが、構造の違いが音にとても影響してると感じたワィ!
だが、ギターを選ぶのは、これを見ているキミぢゃ!
音で選ぶも良し、ルックスで選ぶも良し、弾き心地で選ぶも良し。
是非、実際に手にとって、そして、弾いてみて、感じて、欲しいのぅ♫
実際に比べてみると、それぞれどんなサウンドを持っているのか、違いがわかりやすいですね。動画での博士のコメントも含め、それぞれの音の印象とシーンでの使われ方をまとめてみました。※テレキャスター・シンラインなどソリッドギターをくり抜いた構造のギターもセミアコと分類されますが、ボディ以外の構造はおおむねソリッドギターに準拠しており、まとめが煩雑になってしまうためあまり考えないようにしています。セミアコとソリッドの中間に位置するギターだと考えてください。
| ソリッド | フルアコ | セミアコ | |
| 代表機種 | ストラトキャスター レスポール テレキャスター など |
ギブソンL-5 グレッチ6120 など |
ギブソンES-335 など |
| 今回博士が使用したギター | Sadwsky R1 Custom | Heritage Sweet 16 | Gibson ES-335 Custom |
| ギター博士によるサウンドの印象 | 煌びやかで、チャキッとした音。ドライブサウンドとの相性がとても良い。甘い音でジャジーに決めてもいい。 | とても太く、パンチがある、存在感のあるクリーントーン。トーンを絞って指で弾いた丸い音がセクシー。細い音でファンキーなカッティングも良好。 | 甘さの中に「コキッ」としたアタックがある。ほんの少し歪ませてピッキングで音色を操るのが大好き。ドライブサウンドでバリバリにロックしても良好。 |
| 著名な愛用者 | ジミ・ヘンドリックス、エドワード・ヴァン・ヘイレン、イングヴェイ・マルムスティーン など。 |
ウェス・モンゴメリー、ブライアン・セッツアー、デビッド・T・ウォーカー など。 |
チャック・ベリー、B.B.キング、ラリー・カールトン など。 |
| ディストーション | ◎ | △(ハウリングに泣かされる) | ○ |
| オーバードライヴ | ◎ | ○ | ◎ |
| クランチ | ◎ | ◎ | ◎ |
| クリーン | ◎ | ◎◎ | ◎ |
| 生音 | 小(静かな部屋でなら練習ができる) | 大(マイク録りでレコーディングができる) | 中(騒がしくなければ聞き取れる) |
 Sadowsky Metroline R1 Custom
Sadowsky Metroline R1 Custom
フェンダー・テレキャスターやフェンダー・ストラトキャスターのヒット、ギブソン・レスポールの再評価、またHM/HRの定番機でありスタジオミュージシャン御用達となった<ディンキー(スーパーストラト)の登場などにより、現在「エレキギター」といえば大多数の人がこうしたソリッドギターを連想する世の中になっています。 ストラトキャスターもはじめはカントリー向けの楽器として開発されたようですが、ジミ・ヘンドリックス氏の活躍以来、ロックシーンと共に歩み続けるギターになっています。レスポールは本来ジャズ用に開発されましたが、今やロックの王道モデルです。これらソリッドギターの持つ硬質なトーンには澄みわたるクリーンからズムズムのディストーションまで良好に使用でき、あらゆる音楽シーンに対応できる柔軟性があります。それ以前のギターよりサスティン(音の伸び)が豊かでありハウリングがしにくいということから、エフェクターが使いやすいという特徴も持っています。
HORSE The Band ‘Lord Gold Throneroom’ live in London // BeatCast Live Series
「ニンテンドーコア」は、ハードコアと8ビットゲーム音を融合させたジャンルです(欧米では、家庭用据え置き型ゲーム機を全て「ニンテンドー」と呼んでいるそうです)。さまざまな形態の音楽が輩出していますが、ハードロックやハードコアなどパワフルなサウンドはソリッドギターの独壇場です。
 Heritage Sweet 16
Heritage Sweet 16
いっぽうフルアコはジャズバンドで使われるギターを大音量化するという目的で開発され、アコースティックギターにピックアップをとりつけるという作り方をしています。「ハコ鳴り」の影響を受けた弦振動をキャッチするのでサウンドには「エアー感」があり、太さのあるクリーントーンが得られます。ギブソン系ではトーンを絞った「甘く柔らかいメロウな音色」のイメージが強いですが、トーン全開で弾くとピッキングのアタックに丸みを帯びた太い音が乗るため、パンチ力があります。クリーントーンでの演奏を前提としていますから、歪みが良好なのはクランチまでで、それ以上歪ませるとハウリングに悩まされることになります。
ブリッジの構造などの要因からソリッドギターほどのサスティンは得られませんが、逆に心地よい減衰の仕方が魅力です。またもともとアコースティックギターであることから、ピッキングの強弱による音量変化やピックの入射角による音色変化が非常に豊かであり、音の分離が良くコードの響きに優れています。
甘く、くつろぎのあるトーン「フルアコースティックギター特集」
 Gibson ES-335 Custom
Gibson ES-335 Custom
セミアコの歴史は1958年、ソリッドボディとホロウボディの両方の個性を併せ持つ、全く新しいギター「ギブソンES-335」の登場で始まります。ホロウボディ特有のエアー感、コードの美しさ、ピッキングニュアンスの豊かさを残しながら、ソリッドギター特有の立ち上がりの鋭さとサスティンの長さ、またハウリングへの強さが加わり、ボディが薄くて弾きやすいことからたちまち評判になりました。
セミアコは「ソリッドとフルアコの中間」というイメージですが、センターブロックの存在感が大きいものはソリッド寄り、小さなものはフルアコ寄り、というように設計によってサウンドのキャラクターが変化し、各ブランドの工夫が光るポイントになっています。
豊かで、力強いトーン「セミアコースティックギター特集」
次に、ソリッドギター、フルアコ、セミアコの構造的な特徴を、それぞれの比較をしながらチェックしていきましょう。
| ソリッド | フルアコ | セミアコ | |
| ボディトップ | フラットトップ、カーブドトップ、ベベルドトップ | アーチトップ | アーチトップ、フラットトップ |
| ボディ材 | アッシュ、アルダー、マホガニー、バスウッドなど多岐 | 主にスプルーストップ、メイプルサイド&バック。高級機のトップ&バックは単板削り出し | メイプル、マホガニーなど。ハウリング対策のため合板が使われることが多いが、逆にスプルースがトップ材に使用されることも |
| ボディの作り方 | 板を切る | 板を貼り合わせる | 板を張り合わせるものと、厚い板をくり抜くものとがある |
| 内部構造 | 木が詰まっている | 空洞だが、ブレーシングが貼られる | 中央に木製のセンターブロックを持つ |
| ボディ厚 | 45㎜程度が基本 | 60㎜程度が基本 | 45㎜程度が基本 |
| ボディ形状のバリエーション | 変形など極めて自由度が高い | ボディ幅16インチ、17インチなどのボディサイズ。またホーン先端の形状に違いがある | 定番機の形状に由来したシェイプになる |
| 本体重量 | 木材の重さに準拠する。3kg近辺から5kgほどまで | 電気部品が追加されている分だけ、同サイズのアコギより若干重い | センターブロックの大きさにより上下するが、だいたい4kgまで |
| カッタウェイ | ほとんどのものに有り | カッタウェイ無し、またはシングルカッタウェイが基本 | ダブルカッタウェイが大多数 |
平らなボディトップを「フラットトップ」と言います。一般に完全に平らなトップをさす言葉ですが、右肘の当たる部分を斜めにカットする「エルボーカット」を施したものも、分類上はフラットトップになります(PRSでは、フラットトップの外周部分を斜めにカットしたものを「ベベルド(beveled:傾斜をつける)トップ」と称しています)。
ソリッドボディで曲面を描くトップは「カーブドトップ(carved top)」と言われますが、これは表面を「彫刻する(carve)」のが由来であり、「曲線(curve)」とは異なります。一方「アーチトップ(arch top)」で使われる「アーチ(arch)」は内側も曲面を描いているという意味で、単板削り出しも合板を曲げたものもアーチトップと言われます。
ソリッドギターのボディは板を切るだけなので、その形状にはストラトやレスポールなど定番からフライングVやモッキンバードなどの変形まで多岐にわたるバリエーションがあり、シルエットだけでどんなギターか判別がつきます。反面フルアコ/セミアコのボディ形状は定番のスタイルがほぼ決まっています。
YES – Astral Traveller
イギリスを代表するプログレッシブロックバンド「Yes」のスティーヴ・ハウ氏は様々なギターを持ち替えてプレイしますが、その中にフルアコの代表機ES-175が入っているのは特筆に値します。さすがにディストーションは使いにくいですが、ジャズでの演奏を想定したギターであっても好きなようにプレイしてよいという好例です。
板を切るだけのソリッドボディ、アコギ同様に板を張り合わせるフルアコに対し、
・板を張り合わせたボディ中央に木製ブロックを配置。ES-335など
・分厚い板をくり抜き、板で塞ぐ。リッケンバッカー、テレキャスター・シンライン、ギブソンES-336など
セミアコのボディには二つの作り方があり、貼り合わせたものにはフルアコ寄りなニュアンスが、くり抜いたものにはソリッド寄りなニュアンスがあるとされています。
| ソリッド | フルアコ | セミアコ | |
| ネック材 | フェンダー系はメイプル、ギブソン系はマホガニー | 王道モデルではメイプル3層が基本。マホガニーもあり | マホガニーが基本 |
| 指板材 | メイプル、ローズ、エボニーなど多岐 | エボニーが基本 | ローズを基本とし、高級機はエボニー |
| ボディ/ネックジョイント法 | ボルトオン、セットネック、スルーネック | セットネック | セットネック |
| 弦長 | ショートスケールからエクストラロングスケールまで多岐 | ロングスケールかミディアムスケール | ミディアムスケールが基本 |
| 弦 | ラウンドワウンド弦。いわゆる普通のギター弦 | ジャズでは「フラットワウンド」弦が普通 | ラウンドワウンド弦 |
ソリッドギターとセミアコのネックについては、
とだいたい決まっています。ソリッドギターではこれを基準としながら、ウェンジやローズウッドなどいろいろな木材が積極的に使用され、またショートスケールから極端に長いエクストラロングスケールまで、さまざまな寸法が使われます。ネック強度が特に必要なモデルには3層や5層などの多層ネック、さらには補強用の芯材が採用されることもあります。
フルアコはこの基準に収まりませんが、これはフルアコの源流だったピックギターが「ヴァイオリンを参考に設計されたアコースティックギター」だったことに由来します。ヴァイオリンはメイプルセットネック、エボニー指板、メイプルサイド&バック、スプルーストップというマテリアルであり、ピックギターはこれをそのまま受け継いでいます。強度確保のために多層ネックが基本スペックとなり、またジャズバンドで鳴らすアコギとしての音量が必要だったため、弦長が確保されています。
巻弦でもつるつるな表面を持つ「フラットワウンド」弦が使用されるのも、ヴァイオリンの名残です。断面の丸い線を巻きつけた「ラウンドワウンド」弦より音量が抑えられますが、アタック感もマイルドになってメロウなトーンを出しやすくなります。
今やジャズギターの定番とされているフルアコ「ギブソン ES-175」はマホガニー1ピースネック、ローズ指板、ミディアムスケールですが、これは王道モデル「L-5」の廉価版という位置づけでした。現在では希少となったマホガニーも開発当時には安価に手に入り、またネック材を3枚貼り合わせる工程を踏まないため加工の手間が省かれ、また初心者にも弾きやすい弦長が選ばれました。
| ソリッド | フルアコ | セミアコ | |
| ピックアップ | シングルコイル/ハムバッキングなど組み合わせのバリエーションは多岐。電池を使用するアクティブサーキットを擁するものも | ハムバッカー、P-90を基本とし、ミニハムが使用されることもあり、フロントのみ仕様が目立つ。フローティングピックアップが使われることも | 主にハムバッカー2基もしくはP-90が2基 |
| ブリッジ | シンクロ、TOMなど多岐。ボディの裏から弦を通すことも多い | ボディに乗っているだけのもの。テールピースはボディエンドに引っかけるもの | ストップテールピース&TOMブリッジ |
| トレモロ | シンクロ、ケーラー、FRT、ビグスビーなど多岐 | ビグスビー | ビグスビー、ケーラー |
ここまでソリッドギターに対しては何度も「多岐」という言葉を使っていますが、フルアコ/セミアコと比べてソリッドギターがいかに柔軟なのかがわかりますね。ソリッドギターにおいては、楽器ごとのコンセプトで多様なピックアップが採用されます。ハコモノほどボディ本体の音響性能に神経質ではないため、電気部品をいくつも使う複雑な回路が搭載されることがしばしばあり、電池やプリアンプを使った「アクティブサーキット」も多く見られます。
 フルアコ:Heritage Sweet 16ではフロント1基のみのピックアップ
フルアコ:Heritage Sweet 16ではフロント1基のみのピックアップ
いっぽうハコモノではボディ構造を活かすため、電気系はシンプルにまとめられるのが普通です。特にフルアコではアコースティックギターとしての性格を重視するため、ピックガードにピックアップとボリューム/トーンポットをマウントし、ボディへの影響を最小限に抑える「フローティングピックアップ」が使われることも多くあります。
フレデリック「オドループ」Music Video | Frederic “oddloop”
クリーン/クランチをメインとするサウンドにおいては、セミアコのトーンが大変に有用です。音色の絶妙な太さがバンドによくなじみ、小編成のバンドでも寂しさを全く感じさせません。
ソリッドギターではボディの頑丈さがあり、パーツを載せるためにボディに穴をあけたりネジ留めしたりといった加工に十分耐えることができます。その剛性を活かして、
といったブリッジ/トレモロユニットが採用されます。こうしたブリッジは激しいプレイにも耐えることができるため、チョーキングが必須となるロック系の音楽に特に良好です。セミアコも中心部分はソリッドになるので多様なブリッジを搭載する可能性がありますが、それでもTOMのみなのは、王道モデルES-335の仕様を踏まえているからです。
薄板の箱でできているフルアコの場合、原形となったヴァイオリンの構造を踏襲し、ブリッジとテールピースがボディに固定されないことがほとんどです。ブリッジもテールピースも弦の張力で留まっているだけなので、弦を緩めると外れてしまいます。
フルアコのブリッジはネジ留めされることなくボディトップに乗っているだけなので、位置を移動させてオクターブ調整をすることができます。しかしこの構造からチョーキングなど弦に力がかかるプレイでも位置が移動してしまい、演奏中にチューニングが大きく崩れてしまうことが多々起きます。このことからフルアコをメインに使用するジャズプレイヤーがチョーキングをすることはほとんどなく、「ジャズはチョーキングをしないもの」と思われることが多くあります。いっぽうグレッチなどロック系で使用されることが前提のギターでは、ボディに突起をつけてブリッジの位置を安定させる工夫がなされます。
ハコモノのトレモロは、ビグスビーが定番になっています。取り付けにボディの加工を必要としないことが大きなメリットですが、それ以上に「雰囲気のあるルックス」が極めて大きなメリットになっています。ビグスビーはソリッドギターにも取り付けることができます。
以上、3タイプのギターを比較し、特徴の違いをチェックしてみました。ボディ構造だけでなく、さまざまなところに違いがありましたね。音色の違いから、その楽器のポテンシャルを発揮しやすいジャンルや演奏方法も分かれていきます。ギターそれぞれが得意とする音色で演奏を楽しんでもいいですし、ちょっとイメージと違うサウンドに挑戦しても面白いですね。

ギターの売れ筋を…
Aアマゾンで探す
R楽天で探す
Sサウンドハウスで探す
※当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品を紹介しています。

guitar-hakase.com

guitar-hakase.com

guitar-hakase.com

guitar-hakase.com

guitar-hakase.com

guitar-hakase.com

guitar-hakase.com

guitar-hakase.com

guitar-hakase.com

guitar-hakase.com

guitar-hakase.com

guitar-hakase.com

guitar-hakase.com

guitar-hakase.com

guitar-hakase.com

guitar-hakase.com
