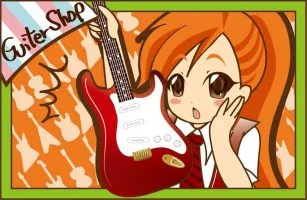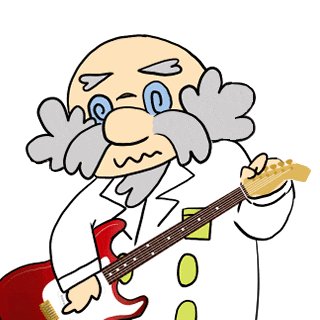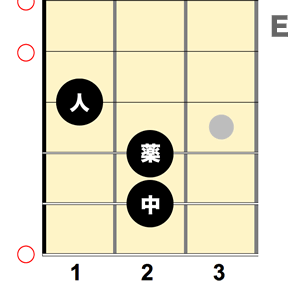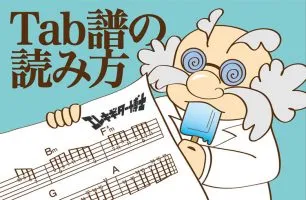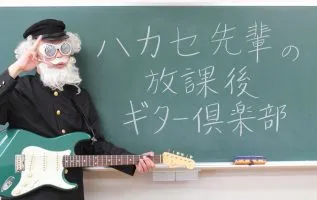エレキギターの総合情報サイト
エレキギターの総合情報サイト
 六弦かなで©
六弦かなで©
エレキギターには、さまざまな形や音の特徴を持ったモデルが存在します。「どんな種類があるの?」「最初の1本はどう選べばいいの?」と迷っている方も多いはず。
本記事では、エレキギターの基本的な構造や代表的なタイプの特徴、選び方のポイントまでを初心者にもわかりやすく解説します。
ギター選びで後悔しないためのヒントを、ぜひここで見つけてください!
名古屋大学法学部政治学科卒業、YAMAHAポピュラーミュージックスクール「PROコース」修了。平成9年からギター講師を始め、現在では7会場に展開、在籍生は百名を超える。エレキギターとアコースティックギターを赤川力(BANANA、冬野ユミ)に、クラシックギターを山口莉奈に師事。児童文学作家、浅川かよ子の孫。

webサイト「エレキギター博士」を2006年より運営。現役のミュージシャンやバンドマンを中心に、自社検証と専門家の声を取り入れながら、”プレイヤーにとって役立つ情報提供”を念頭に日々コンテンツを制作中。
エレキギターにはたくさんの種類やモデルがありますが、その前にまず「そもそもギターってどういう楽器なのか?」を簡単に知っておくと、選ぶときの視点が大きく変わってきます。
ここでは、エレキギターの基本的な構造や、アコースティックギター・ベースギターとの違いなど、ギター選びの第一歩として押さえておきたい基本事項を解説します。
エレキギターは、いくつものパーツが組み合わさってできていて、それぞれにちゃんと意味と役割があります。
それぞれのパーツがどんな働きをしているのかを知っておくことで、ギター選びや演奏のときにもきっと役に立ちます。

ネックより上の部分のこと。ペグが取り付けられている他、ブランド名が入ることが多い場所です。また、弦を響かせる働きをする部分でもあります。
ヘッドに装着しているペグは、弦を巻き付けるための金具。ペグを回して(弦を緩める/締めることで)音程を合わせる作業(チューニング)に使います。
手で握り込んで弦を押さえる部分。ギターの種類によって太さや長さなどが異なります。手が小さくてギターがちゃんと弾けるかどうかが心配な人は、なるべくネックが太くないギターを選ぶのも選択肢の一つです。

各弦が外れないように、弦を支える支柱の役割を果たすパーツ。牛骨・象牙・金属などの素材が使用され、ギターのサスティーン(音の伸び)の量や開放弦の響きに影響を与えます。
ネック上の弦を押さえる方に貼り付けられている板。表面に丸み(アール)がつけられたもの、ほとんど平らな物などが存在し、アールのつきかたによって弾いた時の感触/弾き心地が異なります。
標準的な指板材は以下の3種類。材質によってサウンドの特徴も異なります。

メイプル指板:明るい色が特徴的の指板材。サウンドは硬く、音の立ち上がりが速い、クリアでアタック感が強い。

ローズウッド指板:茶褐色の指板材。メイプル指板のものより柔らかく甘くてソフトな音が特徴で、アタック感はメイプルと比較して少しだけ弱く、温かみのあるサウンド。

エボニー指板:深く濃い色が特徴の指板材。高級ギターに使われることが多い。重く硬く、ローズウッドよりも引き締まったサウンドが特徴。
指板の上に打ち付けられている金属の棒のこと。音程を決めるために取り付けられていて、1フレットごとに半音階ずつ上昇します。22フレットを中心に、21フレット、24フレットなど、ギターのタイプによってフレットの数が異なります。

これから先、「○弦○フレットをを押さえる」といった表現がよく出てきます。エレキギターの基礎として、各弦の名前やフレットの数え方をここでしっかり覚えておきましょう。
六弦かなで「細いほうが1弦、太いほうが6弦、って考えると覚えやすいよ!!」

エレキギターのボディ、木材の部分です。アルダーやアッシュ、マホガニー + メイプルの貼り合わせなど、ブランドによって使用している木材が異なり、それぞれ音の特性が異なります。
ボディにはキズがつかないようにピックガードというカバーが取り付けられるモデルもあります。
ネックとボディの次に、エレキギターの音を決定づける重要なパーツ。細長い「シングルコイル」ピックアップ、シングルコイルの2倍くらいの太さの「ハムバッカー」ピックアップなどが存在します。
弦振動を伝える台座の部分。エレキギターによってブリッジの種類は様々で、弦高の調整もブリッジで行います。
ギターケーブル(シールド)を挿入する部分。ギターアンプやエフェクターに接続し音を出力します。エレキギターのパーツの中ではトラブルが最も多く、接触不良で音が出なくなるなど重要な問題を引き起こす部分でもあります。
トーン(音のヌケ具合)やボリュームを調節するノブ、ピックアップセレクターなどが配置される場所。エレキギターの種類によって配置されるコントロールが違います。
ギターには大きく分けて「エレキギター」と「アコースティックギター(アコギ)」の2種類があります。
一見似ているように見えるこの2つですが、構造や音の出し方、演奏スタイルに大きな違いがあります。

エレキギターは弦が柔らかいので、「弦が硬くて押さえられない!」ということの起きにくい、弾きやすい楽器です。ギターアンプで大きな音を出したり、エフェクターで様々な音を出す事もできます。バンドで弾いたり他の誰かの楽器と合奏する「アンサンブル」が前提の楽器です。
生音がたいへん小さいため、ヘッドホンを使って練習すれば騒音の問題が起きにくいのもメリットです。ただし、アンプやシールド、エフェクターといった電気製品の取り扱いが日常となることに注意が必要です。

アコースティックギターはエレキギターに比べると少し硬い弦を使用しますが、練習や調整で十分カバーできます。チューナーはともかく本体では電源を必要としないオーガニックな楽器で、楽器だけ持って行ってすぐ弾けるという気軽さが大きなメリットです。
ポップスやロックでは、メロディ弾きよりコード弾きで多用されます。コードを鳴らして自分で歌えば、それで「弾き語り」という音楽が成立します。また、自分で弾くメロディに自分で伴奏する「ソロギター」も盛んに行なわれます。ボーカルなどの伴奏やバンド演奏でも使うことができますから、お一人様でもアンサンブルでも音楽ができます。
アコースティックギターの種類と選び方 – アコースティックギター博士
エレキギターとよく似た見た目の楽器に「エレキベース」があります。
どちらもバンドで使われる電気楽器ですが、役割や音の出方は大きく異なります。

ギターとベースでは弦の本数が違います。基本的には弦が6本張られているのがギター、4本張られているのがベースです。6本以上弦を張った「多弦ギター」、4本以上弦を張った「多弦ベース」も存在します。


ギターとベースでは守備範囲にしている音域(最も低い音から最も高い音までの範囲)にも違いがあり、ベースの方が低い音域をカバーしています。同じフレットと同じ音を演奏するとベースはギターより1オクターブ低くなります。

ギター/ベースで「よく使用する音域」を表したもの。
ギターでは伴奏用の和音(コード)を演奏するのが主体となります。エフェクターを活用して多彩な音色を駆使することも多く、ギターソロなどのリードプレイ(メロディ演奏)も必要とされます。
対するベースは「ボトムを支える」と表現されるように、バンドで出す音の最も低いところを主に狙って演奏します。ドラムと合わせて「リズム隊」と呼ばれ、バンドの「ノリ(=グルーヴ)」をつかさどります。ベースの低音はスマホのスピーカーでは聞きとりにくいこともありますが、ライブ会場では床や壁をズンズンと振動させるほどの存在感を発揮します。

ギターとベースでは本体のサイズにも違いがあります。ベースはより低い音を出すため、弦が太く長くなり、自然と楽器も大きくなります。
ギターの弦は細く、1弦は約0.2mmほどの極細。1〜3弦はプレーン弦、4〜6弦は巻弦です。一方、ベースの弦はかなり太く、基本的にすべて巻弦になっています。
《初心者必見》 1本目にオススメの4弦エレキベース10選 – ベース博士
ギター本体、特にボディがどのように作られているかで、エレキギターは3つに分類されます。
ここでは、3つのボディタイプ「ソリッド」「セミアコ」「フルアコ」の特徴と違いをわかりやすく紹介します。
 Fender Stratocaster
Fender Stratocaster
エレキギターの中で最も一般的なのが、ソリッド・ボディを持つ「ソリッドギター」です。ソリッドギターのボディは厚みのある一枚板で、名前通りのソリッドなサウンドが得られるのが特徴です。
爆音で鳴らしたり極端な設定で音作りしたりもでき、ロックやポップスを中心に様々なジャンルで使用されます。アンプにつながない状態では小さな音しか出ないのは、夜遅くまで練習したい人にとって大きなメリットです。
 Gibson Byrdland
Gibson Byrdland
板を貼り合わせたり木材を彫り込んだりして作った、アコースティックギターのように中空のボディ構造を「ホロウ・ボディ」と言い、このボディ構造のギターを日本ではフルアコースティック・ギター(フルアコ)と呼びます。
丸みのある音が最大の持ち味で、ジャズ、カントリー、ロカビリー、ソウル、ポップスといったジャンルで使用されます。ボディはアコギ並みに大型で抱え心地もアコギに近く、アンプにつながなくてもある程度の音量が得られます。
 Gibson ES-335
Gibson ES-335
弦の通る中心部分だけソリッドになっている、部分的に中空のボディを「セミホロウ・ボディ」と言い、日本では「セミアコースティック・ギター(セミアコ)」と呼びます。ソリッドギターの硬さとフルアコの丸さを併せ持ったサウンドが持ち味で、ジャズ、フュージョン、ブルース、ファンク、ポップス、ロックなど幅広いジャンルで使用されます。
ソリッドギター/フルアコ/セミアコをギター博士が比較してみた!
ギター博士が「ソリッド」「フルアコ」「セミアコ」の3タイプを実際に弾いて、音の違いや使い心地を解説。リアルな感想もまとめているので、ギター選びの参考にしてみてください!
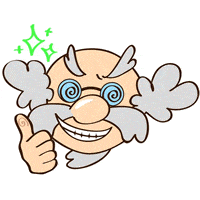
3種類のエレキギターは、構造の違いが音にとても影響してると感じたワィ!
というのがワシの印象じゃ。
音で選ぶも良し、ルックスで選ぶも良し、弾き心地で選ぶも良し。
是非、実際に手にとって、そして、弾いてみて、感じて、欲しいのぅ♫
エレキギターにはいろんな「形」や「モデル」がありますが、大きく分けるといくつかの代表的なタイプに分類されます。
音の特徴や弾き心地、見た目の印象などはタイプごとにけっこう違うので、ここでそれぞれの特徴をざっくり知っておきましょう。
好きなアーティストが使っているモデルや、自分のプレイスタイルに合いそうなタイプを見つけるヒントになりますよ。
8本のエレキギターでギター博士のテーマを弾いてみた!
ギター博士がさまざまなタイプのギターを弾き比べています。それぞれのギターの特徴を知るためにも、登場する8本のモデル名を覚えておきましょう。
ストラトキャスターやテレキャスターに代表される「フェンダー系ギター」は、明るくキレのあるサウンドと扱いやすさが特徴です。
軽めのボディやスリムなネックは初心者にも人気で、ポップスやロック、ファンクなど幅広いジャンルで使われています。
レスポールやSGなどに代表される「ギブソン系ギター」は、太くて重厚感のあるサウンドが魅力です。
ハムバッカー・ピックアップによるパワフルな音は、ロックやハードロック、ブルースなどでよく使われています。
フェンダー系やギブソン系以外にも、個性的なデザインやサウンドを持ったエレキギターがたくさんあります。
音の方向性に独自性があるギター、よりハードなジャンル向けのモデル、モダンな仕様の多弦ギターなど、そのバリエーションは多彩です。
 Jackson JS Series JS22-7 Dinky
Jackson JS Series JS22-7 Dinky
低音側に弦を追加した「7弦ギター」は、テクニカル/ヘヴィなプレイスタイルを取り入れたバンドで使用され、今やヘヴィ・サウンドのための必須アイテムになっています。
Ibanez(アイバニーズ)を中心として様々なメーカーがリリースしていますが、現在では7弦専門のギターブランドまであるほど、確立されたジャンルとなっています。
ここまで色々なギターの種類をみてきましたが、どれを選ぼうかなかなか判断がつかないかもしれません。ここからは、ギターの選び方についていくつかの視点から考えていきましょう。
 1万円近辺で手に入れられるエレキギター、Legend「LST-Z」。恐ろしくお値打ちだが、ストラトキャスターとしての機能を全て持ち合わせている。
1万円近辺で手に入れられるエレキギター、Legend「LST-Z」。恐ろしくお値打ちだが、ストラトキャスターとしての機能を全て持ち合わせている。
エレキギターは数万円の入門モデルから、数十万円を超えるプロ仕様まで、価格の幅がとても広い楽器です。初心者が最初の1本を選ぶ場合は、2〜5万円台のエントリーモデルがおすすめ。この価格帯でも、練習に十分な品質とサウンドを備えており、セットで購入すればアンプやケースなども揃えられます。
エレキギター初心者セットとは?購入前に知っておきたい基本情報
5〜10万円台になると、より良い木材やパーツが使われ、長く使えるクオリティのモデルが多くなります。音の安定感や弾きやすさも向上し、ライブにもにも対応できるレベルです。
どの価格帯でも、見た目や持ったときのフィーリングを大切にすると良いでしょう。
ギター選びのヒントとして、実際にギタリストの愛機をチェックしてみましょう。ここではエレキギターを「王道スタイル」「モダン・ハイスペック系」「ハイゲイン特化タイプ」という3つに分類し、アーティストの動画と共に、いろいろなギターのイメージを掴んでみましょう。
 左から、Fender「Stratocaster」、「Telecaster」、「Jazzmaster」、Gibson「Les Paul Standard」、「SG」、「ES-335」。
左から、Fender「Stratocaster」、「Telecaster」、「Jazzmaster」、Gibson「Les Paul Standard」、「SG」、「ES-335」。
ストラトキャスターやレスポールなど、おおむね1960年代までに発明されて今なお作られているギターが、トラッドな王道系と見られています。これらのギターは長きにわたって音楽の歴史を支えてきた実績があり、存在自体に説得力があります。
遠い昔の設計であり現代の感覚では万能ではないかもしれませんが、逆に「キャラが立っている」と好意的に解釈され、最新のポップスでも圧倒的な人気を誇ります。半世紀前の設計をそのまま現代に伝えるモデルも、現代のシーンに合わせたアレンジが施されるモデルもあります。
主にコードを弾く演奏スタイル
羊文学 – more than words (Official Music Video) [TVアニメ『呪術廻戦』「渋谷事変」エンディングテーマ]
アルペジオやコードストローク、カッティングなど、ギターが主にコード弾きを担当するバンドの場合、トラッドなギターは特に絵になります。この動画で使用されているフェンダー「ジャガー」はショートスケールなので、手の小さい人でも比較的ラクチンにコードを押さえることができます。
ロックンロールなど、トラッドな曲調
The Birthday – LOVE ROCKETS【MV】(映画『THE FIRST SLAM DUNK』オープニング主題歌)
ロックンロールやアメリカン・ポップスなど古き良きスタイルのバンドには、トラッドなギターが最適です。ギターは弾いてナンボではありますが、そのルックスでもバンドや音楽性を演出することができるわけです。
バンド内の役割が明確
sumika / ふっかつのじゅもん【Music Video】
このバンドにはギタリストが二人いますが、目が慣れてくるとこうした場合、どちらがギターボーカルでどちらがリードギターなのか、構えているギターを見るだけでだいたいの判別が付きます。トラッドなギターはそれぞれに明確な個性があるため、ギタリストのキャラクターを演出する効果があります。
 左から、YAMAHA「Pacifica」、Bacchus「BSH」、Fujigen「EOS」、Fender「Stratocaster HSS」、Ibanez「AZS」、EDWARDS「E-Snapper」。
左から、YAMAHA「Pacifica」、Bacchus「BSH」、Fujigen「EOS」、Fender「Stratocaster HSS」、Ibanez「AZS」、EDWARDS「E-Snapper」。
1970年代以降に考案された、トラッドなギターを改造したり性能を向上させたりしたギターが、いわゆるモダンギターです。PRSやリアにハムバッカー・ピックアップを載せたHSSストラト、スーパーストラトがその代表例で、鋭い音から図太い音まで出せる万能性や、プレイヤーのストレスを軽減させる弾きやすさが持ち味です。ギター本体に新しい時代の到来を感じさせる雰囲気もあり、ロック系のアーティストに多く愛用されます。
大胆な場面転換を駆使する現代的なロックサウンド
ONE OK ROCK: Wasted Nights [OFFICIAL VIDEO]
モダンギターの多くで、ハムバッカー・ピックアップの太い音と、これをコイルタップしたシングルコイル・ピックアップの鋭い音の両方が使えます。使えるサウンドの幅が広いので、繊細なアルペジオからヘヴィなグルーヴまでの大胆な場面転換を演出できます。
あえて、欲しい機能に絞る
Hump Back – 「拝啓、少年よ」Music Video
HSSストラトはストラトキャスターのルックスや演奏性をそのままに、ハムバッカーの図太いサウンドが利用できます。ギターボーカルの林萌々子(はやしももこ)さんはこのギターのリアピックアップのみ使用、コントロールノブも取り外しています。好きな機能しか使わない、というのも音楽のためには正しい使い方です。
 左から、Ibanez「RG」、Killer「Exploder」、Schecter「Hellraiser」、Jackson「Dinky」、Charvel「So-Cal」、Epiphone「Flying V Prophecy」。
左から、Ibanez「RG」、Killer「Exploder」、Schecter「Hellraiser」、Jackson「Dinky」、Charvel「So-Cal」、Epiphone「Flying V Prophecy」。
ヘヴィ・メタルに端を発するヘヴィ・ミュージックにおいて、エレキギターは独特の進化を遂げています。速弾きや高速リフなど運動量の多いプレイに有利な設計が採用されるほか、弾きやすさやストレートなサウンドのため、あえて機能やサウンドバリエーションを絞る設計も多く採用されます。キリっと尖ったルックスも特徴的です。
強力なディストーションサウンド
[MV]Dive in Your Faith / Fear, and Loathing in Las Vegas
ヘヴィ・ミュージックにおけるエレキギターは、第一に強力なディストーションサウンドが求められます。そのためパワフルなハムバッカー・ピックアップの搭載が基本で、キレの良い高速の演奏に向けて固定式ブリッジを採用する、トーン回路を非採用など、ポイントを絞ったギターが多く用いられます。
音楽のための特別な設計
[Official MV] Unlucky Morpheus「Black Pentagram」
こうしたヘヴィな演目には、やはり7弦ギターが必要になります。また、過激なアーミングのためフロイドローズ・トレモロシステム(FRT)など高性能な部品を搭載する例が多く見られます。またさまざまなジャンルに細分化されるメタルですが、黒ずくめのファッションと黒いギターは、全メタルに通底する美学のひとつになっています。

実際に楽器屋さんへ行ってみるのも、ギター選びの大事な体験です。弦やピックの購入、調整や修理など、今後もお世話になる機会は多く、信頼できるお店を見つけておくことはとても大切です。
店員さんに相談すれば、予算や好みに合ったギターを紹介してもらえますし、試奏やサウンドの確認も可能です。
弾けなくても大丈夫。気になるギターがあれば、店員さんに代わりに音を出してもらうこともできます。
気になったギターがあったら遠慮せず店員さんに言って、弾かせてもらいましょう。ちょっとしか弾けなくても、全く弾けなくても、実際に触ってみるという体験には非常に大きな意味があります。今まで一度もエレキギターに触ったことがないならなおさら、触らせてもらいましょう。
ズシっと来る重さや予想以上の弦の細さ、ネックのさわり心地など、画面越しに見るだけでは知ることのできない色々なことがわかります。

六弦かなで「ギターに触ったこともないのに店員さんに声をかけたり弾かせてもらうのって勇気がいると思う。そんな時は眺めているだけでもいいと思う☆実際にお店に来ないとわからなかった発見があるかもしれないよ🥰」
近くに楽器店がない場合や、欲しいギターが遠方にしかないこともありますよね。実物を見て買うのが理想ではありますが、いまやネット通販でギターを購入するのも当たり前になっています。選択肢も豊富で、修理や調整を通販ショップに依頼することも可能です。
多くの店では発送前に状態をチェックし、弦の張り替えや万一のトラブルへの対応も行っています。通販を利用する際は、万が一のときのサポート体制も事前に確認しておくと安心です。
いろいろチェックしてみた結果、気になっているギターが、自分のスタイルや出したい音とは違う方向性を持っていたかもしれません。しかしだからといって、その気になっている一本を候補から除外しなければならないということにはなりません。むしろ「でも、好き!」という恋に似たピュアな感情って、何にも代えがたい尊さがありますよね。
確かにギターは音楽を演奏する「道具」ですが、いっしょに音楽を楽しむための「相棒」でもあります。これから長く付き合う相手ですから、機能やグレードばかりでなく「自分がいかにそのギターを気に入っているか」も非常に重要です。
フィーリングで気に入って、納得して手に入れたギターには、深い愛着が沸くはずです。愛せる1本を選んで、最高のスタートを切ってくださいね。
※当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品を紹介しています。